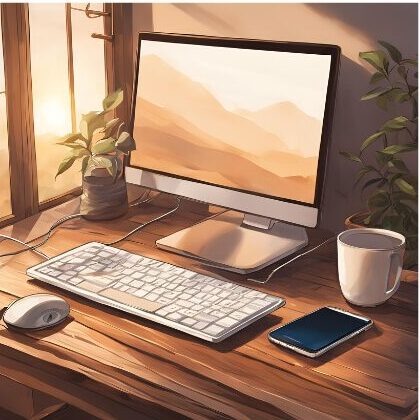「左右差」は希望 | ウェイトトレーニングで見える成長のサイン

走る、跳ぶ、投げる――自分の能力を際限なく発揮することをアスリートは求められます。
でも、多くの選手が気づかずに見落としていることがあります。それは、左右のバランスの差です。
日常の練習で、片方に偏ったフォームや力の入り方はなかなか見えません。
感じてはいるものの、どうすれば改善できるのかも分からない方が多くいらっしゃいます。
でも、ウェイトトレーニングを取り入れることで、その微妙な差がはっきりと見えてきます。
そして、左右差に気づき、弱い方を補強することで、単純に筋力がつくだけでなく、使い方が改善され、走りやジャンプのパフォーマンスがぐっと伸びたりします。
だからこそ、左右差は“伸びしろ”であり、今後の希望でもあります。
そんな未来を、ウェイトトレーニングは教えてくれます。
左右差は悪なのか?
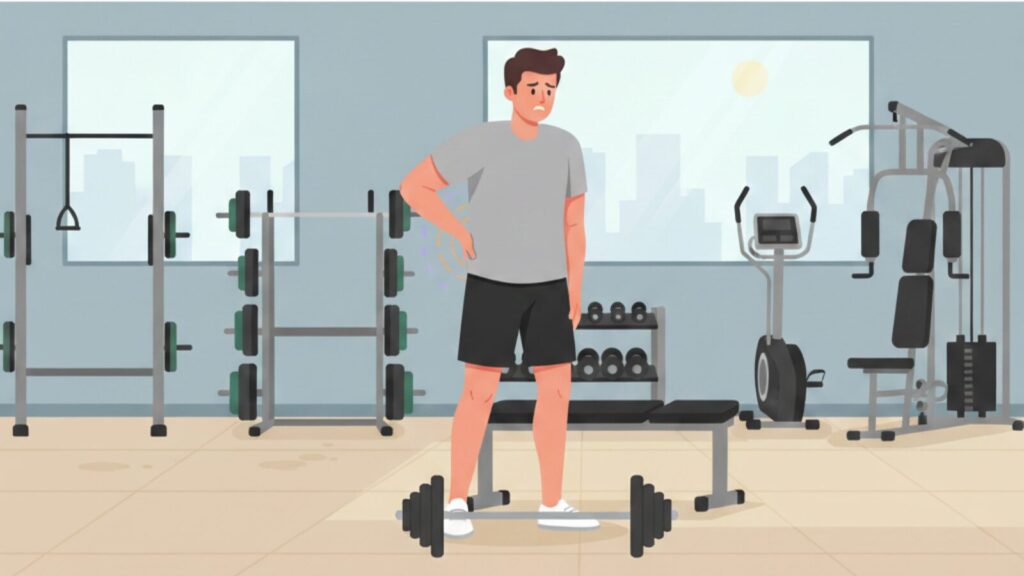
左右差と聞くと、あなたはどんな印象を抱くでしょうか?
「直さないといけないもの」
「怪我の原因になるもの」
「パフォーマンスを下げるもの」
もちろん、そう考える人も多いと思います。
ですが、僕の意見は少し違います。左右差は必ずしも悪ではありません。
そもそも、人間の身体は左右対称には作られていません。心臓は左にしかありませんし、内臓も完全には対称ではありません。
表層的な筋肉は左右均等に付いているものが多くありますが、実際に左右対称ではない筋肉も存在するし内臓も左右対称ではないので、動作に差が出るのは自然なことなのです。
大切なのは、左右差そのものを悪だと決めつけることではなく、自分の身体のクセや差を理解して今後に活かすこと。
左右差を把握することで、弱い側を補強し、パフォーマンスを伸ばすチャンスが見えてきます。
実際にお客様でも、ウェイトトレーニングの最中に初めて左右差があることに気が付かれます。
こっちの方がやりにくい。
こっちの方が使用感がない。
さまざまな気づきをウェイトトレーニングを通じて得ています。
ほとんどのスポーツでは、左右の筋肉が全く同じ働きをすることはありません。クセがつくのは当たり前です。
だからこそ、そこに気づき、正しく調整することで、今からでも走り・ジャンプ・投げる力がぐっと伸びる可能性はあるのです。
次の項目では、どの左右差を意識して改善すべきか、具体的にお伝えしていきます。
左右差が現れやすいトレーニング

僕がトレーニング指導するときに、左右差のチェックや、その人のクセや身体の使い方を見るときに行うトレーニングを紹介したいと思います。
繰り返しますが左右差は必ず存在し、共存しなくてはなりません。
完全に左右差を無くしたがる方も中にはいらっしゃいますが、かなり時間を割かないと達成できないと思います。
右利きが右手で文字を書きやすいのと同じで、左手で同じように綺麗に書くには多くの時間と労力を必要とします。
それと同じことを各筋肉で行うことが本当に優先すべきことなのか考えた上で参考にしてみてください。
そして、誤解をしてほしくないことは左右差は自然なことであるから放置です。というわけではありません。
放置してたらパフォーマンスを邪魔する左右差は調整が必要ということです。
ブルガリアンスクワット
定番は片足で行うブルガリアンスクワットです。
この種目はメインターゲットはお尻と前ももの筋肉なのですが、正しいポジションに入らないと狙いたいお尻効かせることが難しく、前ももに力が入ってしまったり外ももに力が入ったりする種目です
実際に指導現場でも取り入れることが多いです。
ブルガリアンスクワットで得られるヒントは以下の通りです。
- 片足軸で、グラつかずに床を踏むことができるのか。
- 上半身の姿勢を正常に取れるのか。
- 膝や股関節を捻らずに力を加えることができるのか。
大枠はこの3つくらいをチェックしています。
このチェック項目から、筋力的な問題なのか、ポジションの問題なのか、骨格可動域の問題なのか整理して今後のメニューを組んでいます。
例えば姿勢が崩れてしまうのが、骨格的な問題だった場合、行わなくてはならないのはストレッチなどによる可動域の向上です。
それを筋力向上などで解決しようとガンガン行ってしまうと左右差を助長してしまう可能性があるので注意が必要です。
ワンハンドロウ
背中の左右差をチェックするときはワンハンドロウを行うことが多いです。
まず、多くの方は背中の筋肉を上手に扱うことができません。
収縮感が分からない、使い方が分からない。
ここでの答えは一つだけです。
姿勢が悪いから。
多くの人は猫背で丸まっているので、普段から広背筋が伸ばされていて、収縮することがありません。
反対側の大胸筋の収縮により広背筋の収縮の仕方が分からない、というよりも常に引っ張られているので広背筋の可動域が制限され収縮感を得にくいと言った方が分かりやすいかもしれません。
例えるなら綱引きと同じです。
お互いに引っ張り合う拮抗筋の関係にあるものは基本的には綱引きをしている状態です。
つまり、猫背の姿勢は赤組の大胸筋が優位なポジションで引っ張り続けるわけです。
ですから白組の広背筋は引くに引けなくなっている状態です。
広背筋をしっかり左右差なく使うことは姿勢の改善につながり、結果として自身の競技パフォーマンスも上げてくれます。
また広背筋の機能萎縮や過度な左右差は腰痛の原因にもなりやすく、著しくパフォーマンスを落とすので、背中の機能向上と怪我の防止の観点からワンハンドロウで左右差をチェックするのはおすすめです。
片脚ルーマニアンデッドリフト
ルーマニアンデッドリフトは、お尻を後ろに引きハムストリングを伸長させて背中は姿勢維持のため等尺性収縮をさせるトレーニングです。
これを片脚で行うのも、左右差を大きく炙り出します。
- ハムストリングの柔軟性
- 股関節のヒンジ動作
- 上半身の姿勢維持
- 骨盤の回旋抑制
片脚ルーマニアンデッドリフトは多くの機能が必要とされるので、正しく行うには優れたフィジカルコントロールが要求されます。
まず多くの人は左右差云々の前にトレーニングのコツ習得に時間を要しますが、コツを掴めば先の通り多くの左右差が炙り出され課題が顕著に示される便利なトレーニングです。
また上半身と下半身の役割が揃わないとバランスを崩してしまうため、満足に狙った筋肉に刺激が入りません。
だからこそ習得できれば上半身と下半身の同調が起こしやすく、競技パフォーマンスの向上の一助になります。
最初は自重でも十分ですし、どうしてもバランスを崩してしまう方は補助的に手すりにつかまりながら行うことをおすすめします。
動作に慣れてきたら、両手にダンベルを持って少しずつ負荷を増やして適応を起こしていきましょう。
まとめ : 左右差は伸び代である
いかがでしたでしょうか。
左右差は誰しもが抱えているもので自然現象です。
その上で、開きすぎてしまった左右差は調整が必要にります。
開きすぎた左右差は怪我の原因にもなりますし、競技パフォーマンス時の力の伝達ロスにもなります。
だからこそ大切なのは、自分の左右差をどう認識し、どう付き合うかです。
調整すべきものなのか、許容して良いものなのか、その見極めが成長し続けるための分かれ道になります。
今ある左右差をどう使うかで、未来のパフォーマンスは変わります
しかし、自分の左右差を正しく把握している人はほとんどいません。
逆に言えば、そこにこそ大きな伸びしろが隠れています。
表参道にございますAGELCA personal gymでは、「片足・片腕系の種目」を通じて、あなたの左右差をチェックし、改善のための第一歩を提案しています。
自分の身体のクセを知ることは、思っている以上に大きな発見になりますよ。
ぜひチェックしてみてください。